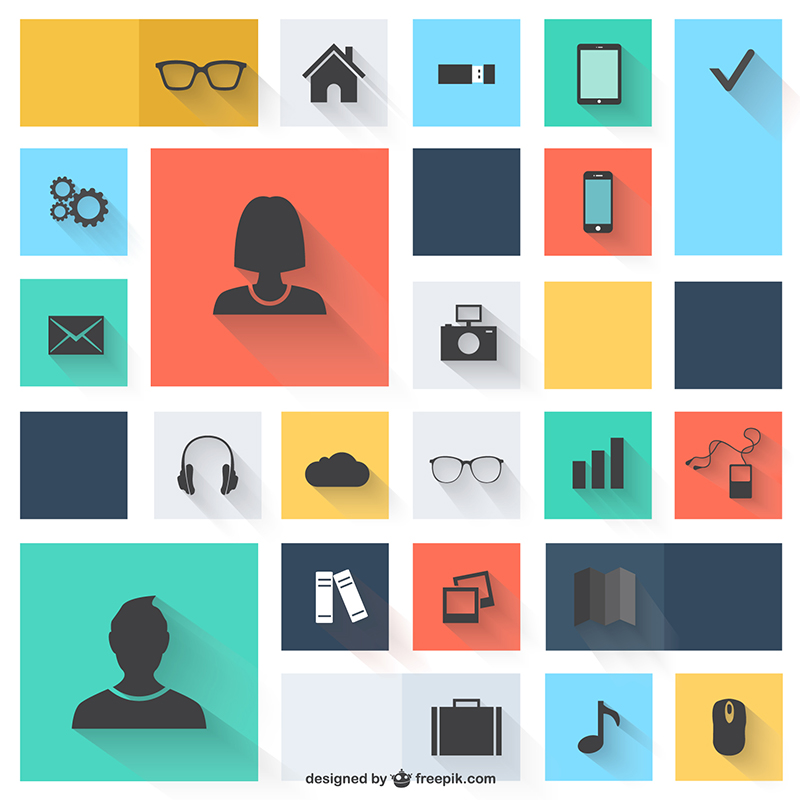
「そうかねえ、わたしはたった一つのあかしだと思っていた。」
「そら、ね、ごらん、そうだろう、それに番号がついてるんだよ。」
わたしたちはしゃがんで花を見ました。なるほど一つ一つの花にはそう思えばそうというような小さな茶いろの算用数字みたいなものが書いてありました。
「ミーロ、いくらだい。」
「一千二百五十六かな、いや一万七千五十八かなあ。」
「ぼくのは三千四百二十……六だよ。」
「そんなにはっきり書いてあるかねえ。」
わたくしにはどうしても、そんなにはっきりは読むことができませんでした。けれども花のあかりは、あっちにもこっちにももうそこらいっぱいでした。
「三千八百六十六、五千まで数えればいいんだから、ポラーノの広場はもうじきそこらな筈なんだけれども。」
「だってさっぱりきみらの云うような、いい音はしないじゃないか。」
「いまに聞えるよ。こいつは二千五百五十六だ。」
「その数字を数えるというのはきっとだめだよ。」
とうとうわたくしは云いました。


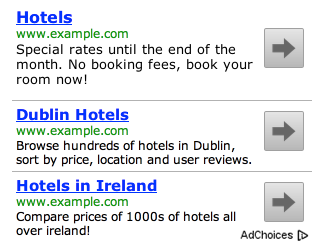


コメントを残す